化粧品のブランド立ち上げや新商品の開発を検討している方にとって、パッケージOEMは重要なステップの一つです。
見た目の印象が売上に直結する化粧品業界では、容器や箱、ラベルのデザイン・品質がブランド価値を左右します。
そこでこの記事では、「小ロットで始めたい」「費用感がわからない」「どこに頼めばいいの?」という疑問を抱える方に向けて、化粧品パッケージOEMの流れや注意点、費用相場、そして失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。
初めてでも安心して依頼できるよう、実例を交えながら具体的に紹介していきますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
化粧品OEMとは?パッケージOEMの意味と特徴

化粧品OEM(Original Equipment Manufacturer)は、依頼者のブランドで化粧品を製造する仕組みです。
なかでも「パッケージOEM」は、既製品の中身を活用しつつ、容器・ラベル・箱などの見た目をオリジナルにカスタマイズできるため、コストを抑えながらブランドイメージを打ち出せるのが特徴です。
OEMとよく混同されがちなのが「ODM(Original Design Manufacturer)」ですが、これは設計から製造まですべてを委託する方式。
一方、OEMは設計は自社や依頼者側が行い、製造のみを任せるスタイルです。
たとえば以下のようなケースでは、パッケージOEMの活用が適しています。
・中身はすでにOEM製造している、または自社で用意できる
・ターゲットや販路別に外装だけを変えたい
・まずは小ロット・低予算でスタートしたい
スキンケアやギフト商品など、パッケージの印象が売上に直結するジャンルでは、外装に注力するOEM戦略が効果的です。
なお、OEMとODMのより詳しい違いや最新動向については、以下の記事で詳しく解説しています。
→【2025年最新版】化粧品OEMとは?トレンド・費用・委託先の選び方など徹底解説
化粧品OEMのメリット・デメリット
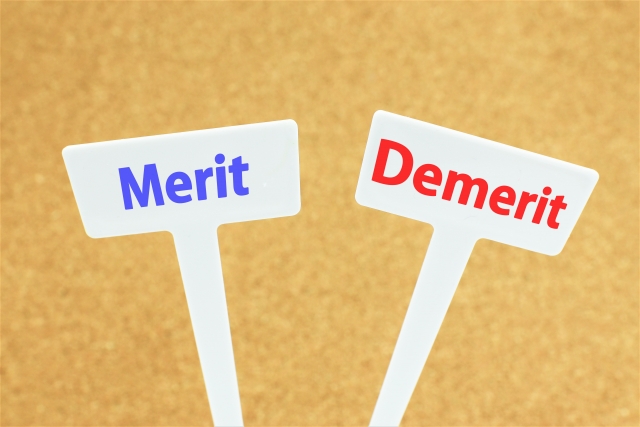
OEMのメリット
OEMには、自社に設備や専門知識がなくても化粧品を商品化できるという利点があります。
特にスピード感とコスト削減の面で、立ち上げ初期には大きな武器となります。
・初期投資を抑えられる
・開発・製造に関する知見や設備が不要
・スピーディに商品化が可能
OEMのデメリット
一方で、外注であるがゆえに品質や納期に関するリスクもゼロではありません。
自社での調整が効きづらい面もあるため、信頼できるOEM先の選定が重要です。
・ロットや納期の自由度に制限が出ることも
・品質管理を委託先に依存するリスクがある
・自社製造と比較してコスト構造が読みにくい
OEMの流れと必要な期間(受注から納品まで)

ステップ① ヒアリングと企画立案
化粧品のパッケージOEMは、ステップをきちんと踏めば初心者でも安心して取り組める仕組みです。
ここでは一般的な流れと、対応にかかる期間の目安をご紹介します。
まずはブランドの方向性や、販売ターゲット、想定の販売価格帯などを相談します。
そのうえで、容器の形状や素材、ラベルの仕上げなどを含めたパッケージ仕様を提案してもらいます。
ステップ② 見積もりと仕様確認
選定した仕様に基づき、材料や数量、加工方法などを確定します。
このタイミングで、納期・費用の見積もりも提示されます。
ステップ③ パッケージデザインの制作
ロゴや商品名、成分表示などのラベルやパッケージデザインを作成します。
自社で用意することも可能ですが、薬機法対応や表示義務に不安がある場合は、OEMメーカー側に依頼する方が安心です。
ステップ④ サンプル作成と承認
モックアップ(試作品)を作成し、仕上がりイメージを確認します。
素材感やサイズ感、カラーの再現性などを最終確認し、必要があれば修正を依頼します。
ステップ⑤ 本発注〜納品
サンプルが承認されたら本発注に進みます。
製造期間は数量や仕様により異なりますが、一般的に数週間〜数ヶ月程度。
当メディアを運営している「I Love Paper Bag」では最短4日〜納品が可能ですが、輸送方法や時期によって納期は変動しますので、余裕を持ったスケジュールを意識することが大切です。
小ロット対応のOEMは可能?

「まずは少ない数から試したい」「在庫リスクを最小限にしたい」と考える方にとって、小ロット対応のOEMは重要な選択肢です。
最近では、「I Love Paper Bag」を含め個人ブランドやD2C(直販)市場の広がりにより、小ロットでの化粧品OEMに対応するメーカーも増えてきました。
小ロットの目安はどのくらい?
OEMメーカーや製品タイプによって異なりますが、以下のような目安があります。
・スキンケア・ヘアケア製品:300〜1,000個から対応可能なメーカーが多い
・メイクアップ用品(リップ・アイシャドウなど):500〜3,000個が一般的
・ギフト用ボックス・限定キット:資材次第で100個前後からも可能な場合あり
ポイントは、「資材の在庫を確保しているか」「既成型(モールド)を活用できるか」によって、最小ロットのハードルが変わるということです。
小ロットで失敗しないための3つのコツ
1. 人気の既成容器を使う
オリジナル金型を使うと初期費用が高くつくため、すでに業界で流通している既成の容器やボトルを選ぶことで、コストも納期も大幅に抑えられます。
2. 印刷ではなくラベル貼りにする
シルク印刷やホットスタンプは高額になりやすいため、小ロットではシンプルなラベル印刷での対応がコスパ◎。
しかも、変更もしやすいためテスト販売にも向いています。
3. 複数SKUを統一パッケージで展開する
香り違いやカラー違いなどの商品展開を考える場合も、ボトルや箱を統一してラベルのみ変えるなどの工夫で、全体コストを抑えつつブランドラインを広げることができます。
【あわせてチェック!】
当ブログを運営している「I Love Paper Bag」でも、100枚からの紙袋印刷・パッケージOEMの相談が可能です。
D2Cブランドや個人事業主の初めの一歩を丁寧にサポートいたしますので「小ロットで始めたいけど不安…」という方はご利用ください。
初期費用の内訳

製品を立ち上げる段階で必要になる初期費用の目安は以下の通りです。
デザイン制作費(約3万円〜10万円)
ラベルや箱のデザインを外注する場合の相場です。法規対応(薬機法など)も含めると高くなる場合もあります。
金型費 ※モールド代(数万円〜十数万円)
容器を完全オリジナルにする場合は必要。
ただし、既製品を使えば不要になるため、小ロットでは避けられることも。
資材費 ※パッケージ資材の仕入れ(注文ロットや仕様により変動)
紙箱やラベル、容器などの資材はロットによって価格差が出ます。
コストを抑えるために意識すること

1個あたりの単価とロット数の関係
OEMにおいては、ロット数が増えるほど1個あたりの製造コストが下がるのが一般的です。
たとえば……
・300個発注 → 単価200円
・3,000個発注 → 単価120円
これは一例ですが、上記のように10倍のロットでもコストは2/3程度に下がるケースがあります。
そのため、長期的に販売を見込める商品であれば、ある程度まとめて発注する方がコストパフォーマンスは高くなります。
コストを抑えるための3つのポイント
以下のような工夫をすることで、初期費用・単価の両面でコストダウンが可能です。
1. 汎用品を活用する
既成の容器やパッケージを活用することで、金型費や特注費用を抑えられます。
業界で流通しているボトルや箱でも、ラベルやカラー次第で十分に差別化は可能です。
2. 加工を最小限にする
箔押し、エンボス、特殊印刷などの装飾はコストが跳ね上がる原因に。
最初はシンプルな印刷やラベルで抑えるのが現実的です。
3. 同じ仕様で複数商品を展開する
容器やパッケージを統一し、中身やラベルだけを変えることで、商品バリエーション(SKU)を広げることもできます。
これにより、資材の仕入れ効率が上がり、結果的に単価が下がります。
このように、ただ見積もりを取るだけでなく「どこにコストがかかるのか」「どこを工夫できるのか」を理解しておくことで、OEMを無駄なく進めることができます。
必要であれば、小ロット・資材OEMに対応している業者などに事前相談しておくのもおすすめです。
OEMメーカーの選び方|小ロット・実績・サポート体制

対応できるロット数で選ぶ
まず確認すべきは、希望ロット数に対応しているかどうかです。
たとえば「まずは300個だけ試したい」という場合でも、最小ロット1,000個〜などの条件があるメーカーも存在します。
ロットに無理があると、コストが跳ね上がったり、納期が長期化したりと、思わぬリスクが生じます。
最初に希望ロットと製品仕様を伝え、柔軟に対応してくれるかをチェックしましょう。
デザイン・法規対応の支援があるか
化粧品は、薬機法・INCI表示・全成分表示など、表記に厳格なルールがあります。
パッケージデザインを外注する場合は、こうしたルールに詳しいOEMメーカーかどうかが重要です。
「ラベルを自社で用意したらNGだった」などのトラブルを避けるためにも、法規対応を含めたトータルサポートの有無を確認しておくと安心です。
過去の実績や事例をチェック
できれば、自社と業態や規模感の近いクライアント実績があるメーカーを選ぶと、やりとりもスムーズです。
たとえば「個人でD2Cブランドを始めたい」といった場合、大手向けOEMがメインのメーカーではミスマッチになることも。
Webサイトに掲載されている事例や、問い合わせ時の対応からも、親身なサポート姿勢かどうかを見極めることができます。
化粧品OEMでよくある失敗と注意点
薬機法表記・成分誤記に注意
前述の通り化粧品のパッケージには、薬機法やINCI表示(国際的な成分表記)などの法規制が厳しく定められています。
しかし、初めてのOEMではデザインを優先するあまり、
・「美白」「シワ改善」などの効果効能表現を誤って記載
・表示義務のある全成分や製造販売元の情報が漏れていた
などといったミスが起こりがちです。
対応策としては、薬機法に精通したOEMメーカーに相談することが最も確実です。
可能であれば、ラベルの最終チェックまでサポートしてくれる会社を選びましょう。
I Love Paper Bagでは、万が一にも薬機法やINCI表示に抵触してしまわないように、お客様に対して相談・アドバイスをお受けしております。
パッケージ品質と中身のズレに注意
たとえば、高級感あるマットブラックのボトルを採用したのに、中身が水のようにサラサラなローションだった場合、「見た目と中身の釣り合いが取れていない」といった不満につながることがあります。
特にD2Cでは、ユーザーは見た目で購入を決める一方、リピートは中身の満足度に依存するため、
このミスマッチはクレームや返品、悪いレビューにつながることも。
OEMを進める際は、パッケージの印象と使用感・成分のバランスを意識したブランディング設計が重要です。
納期の遅れ/トラブル回避のポイント
OEMでは、資材の遅延や印刷工程でのトラブルなどで、予定通りに納品されないケースも珍しくありません。
「予定していた販売日が遅れた」「ECサイトのリリースに間に合わなかった」という失敗も見られます。こうした事態を避けるためには、
・スケジュールをできるだけ前倒しで組む
・途中経過の報告体制を整えてもらう
・万が一の遅延時にどうリカバリーするかを事前に確認しておく
といった事前の取り決めと進捗管理の習慣化がカギになります。
小ロットからスタート → 成功したパッケージOEM事例4選
① HACCI(ハッチ)|はちみつ×コスメのギフト展開で拡大
最初は百貨店のバラ売りギフトや雑貨店での委託販売からスタート。
「はちみつ石けん」や「はちみつボトル入りリップ」など、パッケージの差別化と既存容器のラベル活用でコストを抑えながら高級感を演出。
現在は伊勢丹・セレクトショップ・空港免税店などで展開。
【行なった工夫】
・既成ボトル+オリジナルラベル
・箱も市販サイズを活用+箔押しだけで高級感
② BARTH(バース)|入浴剤ブランドがパッケージ刷新で急成長
OEM製造のバスアイテムを独自ブランド化。
当初はドラッグストアでテスト販売、シンプルなパウチパッケージ+紙スリーブで小ロット展開。
SNSバズ→EC流入→大手店舗へスケール。
【行なった工夫】
・OEMの既成袋を使用
・デザイン性だけで勝負(加工費なし)
③ N organic|通販スタート→パッケージ重視で店舗進出
最初はD2C(自社通販)で、シンプルな化粧箱+茶瓶という低コスト&統一容器で展開。
のちにロフト・東急ハンズ等でも取り扱いスタート。
デザインとストーリー重視のパッケージで認知拡大。
【行なった工夫】
・1つの容器で複数ラインナップ展開
・最小限印刷+ベル貼付
④スキンケアブランドの立ち上げ
【I Love Paperbag】でもパッケージOEMを行っております。
OEMでオリジナル化粧品は本当に作れるのか?

差別化できるポイント3つ
OEMでオリジナル化粧品を作るときに差別化を考えるポイントは大きく3つあります。
・ユニークなデザイン
・天然成分や限定処方
・ストーリー性(製造背景やブランド哲学)
このようにポイントを絞っていくことで、競合他社との差別化が図れます。
以下で上記の内容を含めた具体的な方法を確認していきましょう。
ブランディングを意識したOEM活用法
OEMで成功するブランドの多くは、単に中身やパッケージを作るだけでなく、「ブランドとしての一貫性」まで設計しています。
以下のような点にこだわることで、他社製品との差別化を超えて、ブランド指名買いされる存在へと育てることができます。
1. ブランドの“らしさ”を視覚化する
ロゴ・配色・フォント・パッケージ素材に一貫性を持たせ、パッと見で伝わる個性をつくる。
奇を衒う必要はなくとも、こうした一貫性が「ユニークなデザイン」として認識されます。
例)「環境や社会への配慮」を大切にするエシカルブランド(倫理的な消費を意識したブランド)なら、未晒クラフト紙やFSC認証素材など「素材選び」からその理念を伝えることができます。
2. 使用体験全体をデザインする
開封時のワクワク感、香りや手触り、手に取ったときの重量感など、五感を通じた体験価値を設計。
例)あえて中身は定番処方でも、ボトルや開封順で記憶に残る演出を加える
3. コンセプトと背景をストーリーで伝える
ブランドの「想い」や「背景となる課題」「開発ストーリー」を丁寧に届けることで、ファンの共感を生む。
これがブランディングに大切な「ストーリー性」を生みます。
例)地方の工場との提携や、創業者の体験から生まれたプロダクトストーリーなど
まとめ
化粧品OEMは、初めてでもプロの力を借りれば安心して進められます。
小ロットから始めたい、独自ブランドを展開したいという方は、パッケージの印象がブランドイメージを左右することを忘れずに。
【I Love Paperbag】では、小ロット・短納期にも柔軟に対応したパッケージOEMの相談が可能です。
まずは気軽に、あなたの理想を形にする一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。





