近年、D2Cブランドや個人ブランドの立ち上げが加速するなかで、注目を集めているのが「化粧品OEM」です。
自社で製造ラインを持たなくても、オリジナルの化粧品を作ることができるこの仕組み。
初めて商品開発に挑戦する人にとっても有効な選択肢になっているのが人気の理由です。
しかし、その中身は案外難しかったりして、いざ始めようとすると「費用感は?」「どうやって選べばいいの?」と疑問が山積みになるのも事実。
そこでこの記事では、2025年の最新トレンドやOEMの流れ、費用相場、委託先の選び方まで、初心者でも分かるよう丁寧に解説いたします。
化粧品OEMとは?初心者でもわかる基本解説

化粧品OEM(Original Equipment Manufacturer)とは、自社ブランド名で化粧品を製造できる仕組みのことです。
処方設計から製造、パッケージングまで一括で委託できるため、製造設備や専門知識がなくても、手軽にオリジナル商品を開発できるのが最大の魅力です。
近年では、D2Cブランドやインフルエンサーによるプロデュース商品など、スピード感を重視した展開にOEMが選ばれるケースが急増。
副業や個人ブランドの立ち上げにも適しており、実際に少ロットから始めて人気商品へと成長した事例も多数あります。
OEMとODMの違いとは?
OEMは「依頼主の設計や処方をもとに製造のみを請け負う方式」。
一方でODM(Original Design Manufacturer)は「製造だけでなく、企画や設計の段階からトータルで支援する方式」を指します。
つまり、1から企画・開発まで任せたい場合にはODM、すでに商品イメージがあるならOEMでコストやスピードを優先するのが一般的な選択肢です。
たとえば……
「まずは見た目(パッケージ)で差別化したい」
「中身の処方はすでにイメージがある」
といった場合には、パッケージOEMに強いメーカーを選ぶことで、より効率的な商品開発が可能になります。
ODMほど大がかりな体制を必要とせず、少ない予算で自社ブランドを立ち上げたい人にとってはOEMの方が現実的です。
2025年の化粧品OEM市場トレンド
2025年現在、化粧品OEM市場では次のようなトレンドが顕著です。
・自然派、オーガニック成分
・サステナブル、リサイクル可能な容器
・ヴィーガン処方や動物実験フリー
・小ロット対応、短納期へのニーズ拡大
これらの流れに応じて、OEMメーカーも処方やパッケージの選択肢を広げ、小規模事業者でも本格的なブランド展開ができる環境が整いつつあります。
つまり今は、低リスクで「自分だけのブランド」を立ち上げやすいタイミングと言えるでしょう。
化粧品OEMの流れ|企画から納品までのステップ

化粧品OEMは、「自社ブランドの化粧品を作りたい」というニーズを形にするプロセスです。
ここでは、OEMメーカーに依頼してから商品が納品されるまでの流れを具体的に解説します。
OEMの基本的な進行フロー(6ステップ)
1. 商品企画・ヒアリング
まずは「どんな商品を作りたいのか」を明確にします。
ターゲット、使用感、使用シーン、香り、希望価格帯などをOEMメーカーとすり合わせるフェーズです。
初心者の場合でも、実績豊富なOEM会社であれば、市場動向を踏まえたアドバイスを受けながら企画を形にできます。
例)「敏感肌向けのオールインワンジェルを作りたい」「SNS映えするカラーマスクを出したい」など、ざっくりしたイメージからのスタートでもOKです。
2. 試作・処方設計
ヒアリング内容をもとに、ラボで実際に処方開発・試作品づくりが行われます。
試作品はテクスチャーや香り、色味などを確認しながら複数回の調整を重ねて決定します。
試作段階では、自分自身で使用感を試すことがとても重要です。気になる点は遠慮なくフィードバックしましょう。
3. 見積もり・契約
処方と容器・パッケージの大枠が決まったら、製造ロットや資材費・充填費などの見積もりが提示されます。
納得できれば正式契約へ。
この段階で初期費用や支払いスケジュールをしっかり確認しておくことが重要です。
4. 資材(容器・化粧箱など)の選定・デザイン制作
容器や箱などのパッケージ資材を選定し、ロゴやラベルなどをデザインしていきます。
完全オリジナルでの制作も可能ですが、そのぶんコストと納期はかかるため、既製容器をうまく活用するのも選択肢のひとつです。
近年はサステナブル素材やバイオマス容器の需要も増えており、ブランドのコンセプトに合ったパッケージを選ぶことが差別化につながります。
5. 製造・充填・検品
処方とパッケージが揃ったら、工場にて製造・充填・密封・検品を経て、製品として完成します。
化粧品は薬機法にも関わるため、製造はGMP(適正製造規範)を満たした工場であることが望ましいです。
6. 納品・販売準備
完成品は希望する形で納品されます(化粧箱に入れて完成品状態にする、バルクのままで納品するなど)。
並行して、販売用の広告や商品ページの制作、薬機法表記のチェックなども進めましょう。
リードタイム・納品までの期間はどれくらい?
OEMの納期は、商品ジャンルや資材の在庫状況、試作回数によって大きく変動します。
初回製造の場合は約4〜6ヶ月が一般的です。
・スキンケアなど処方がシンプルなもの → 約3〜4ヶ月
・メイクアップや処方調整にこだわるもの → 約6ヶ月以上かかることも
また、2回目以降は処方・資材が流用できるため1〜2ヶ月での納品も可能です。
ただし、完全オリジナルの容器や海外製資材を使用する場合は納期が長くなるため、事前に確認しておきましょう。
納期遅れの原因で最も多いのが「資材の遅延」です。人気容器や海外製パーツは早めの確保がカギです。
このようにOEMの流れはシンプルですが、準備の段階でどれだけ具体的なイメージを持てるかが成功の分かれ道になります。
パートナー選びと企画の詰めが、納期にも品質にも大きく影響するため、妥協せずに進めましょう。
OEMのメリットと注意点
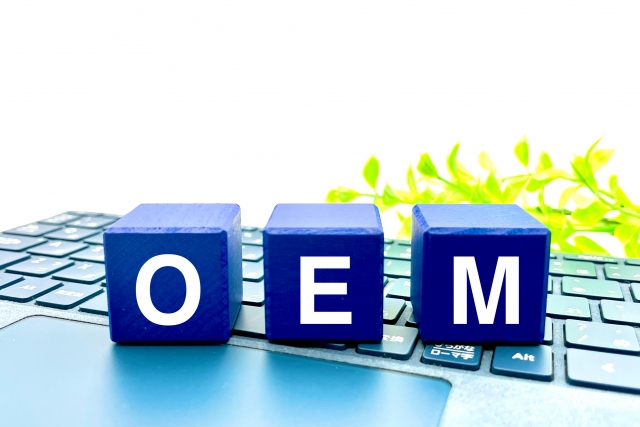
化粧品OEMは「自社ブランドの商品を低リスクで展開できる手法」として注目されていますが、当然メリットだけでなく注意点も存在します。
ここではOEMの利点と注意点をわかりやすく解説します。
OEMを活用する5つのメリット
①自社に製造設備がなくても商品開発が可能
最大の魅力は「製造ラインを持たずに自社ブランド商品を持てる」こと。
特に中小企業や個人事業主でも、初期投資を抑えて事業をスタートできる点が支持されています。
②小ロット対応でリスクを抑えられる
近年は100個〜500個といった小ロット生産にも対応するOEMメーカーが増加。
たとえば当メディアを運営している I Love Paper Bagの場合、化粧品のパッケージだけでなく化粧品の中身もお手伝いすることも可能です。
国内外のメーカーとの取引があるため、お客様のニーズに合わせてお見積りをおとりさせていただいております。
また、その場合、商品にもよりますが最低ロット100個〜可能になっています。
このように小ロットでの生産が可能なOEMメーカーを選ぶことで「まずはテスト販売して反応を見る」「クラウドファンディングやSNSと連携して販売したい」というニーズにも応えられます。
現在は美容系インフルエンサーなどが500個限定でリップを発売 → 数時間で完売 → 増産へといった流れもあるため、比較的誰でも挑戦しやすい活用方法となっております。
③パッケージや成分など自由度が高い
処方(成分)、香り、テクスチャー、容器、箱などをオリジナルで設計可能。
「ヴィーガン処方」「アロマ重視」「無添加」など、ブランドの世界観に合った差別化がしやすいのもOEMならではといえるでしょう。
④ブランディングとマーケティングに専念できる
製造工程をアウトソースすることで、商品企画・デザイン・販売戦略に集中できます。
特にD2C(Direct to Consumer)ブランド(自社で企画・販売までを一貫して行うブランド)やEC運営者にとって、時間とリソースの最適化が図れるのは大きな利点です。
⑤薬機法に対応した製造が可能
信頼できるOEMメーカーであれば、薬機法に沿った製造・表示ルールの確認もサポートしてくれるため、法令違反のリスクも減らせます。
OEMにおける4つの注意点
①小ロットではコスト高になることも
少量生産の場合、容器代・印刷代などが割高になり、1個あたりの原価が高くなる傾向にあります。
価格競争が激しいジャンルでは、収益確保が難しくなることもあるため、販売戦略と価格設定は慎重に。
②処方やデザインには専門知識が必要
OEMでは基本的に「何をどう作りたいか」を依頼主が決めるため、企画段階である程度の知識や方向性が必要になります。
まったくの初心者には、ODM(企画から対応)メーカーの方が向いている場合もあります。
③薬機法・成分表示などの法規制に注意
化粧品は薬機法の対象となるため、広告表現や成分表記に厳密なルールがあります。
OEMメーカーによってはこのサポートが不十分な場合もあり、販売者側にも基本的な知識が求められます。
④トラブル対応・アフターケア体制は要確認
納期遅れ、不良品、仕様変更などが発生した際に、メーカーの対応範囲・保証内容が契約で明確になっているかを必ず確認しましょう。
契約書や仕様書の取り交わしを丁寧に行うことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
OEMは、アイデアと販売力があれば誰でもオリジナル化粧品を作れる非常に魅力的な仕組みですが、正しく理解して使いこなすことが成功のカギとなります。
自分のブランドの世界観や販売戦略にマッチするOEMメーカーを選ぶことで、ブランド価値を高めながら安定的な商品展開が可能になるでしょう。
OEMを成功させるためのポイント

コストダウンの工夫
化粧品OEMにおいてコストを抑えるためには、「見た目」と「中身」のバランスを意識することが重要です。
たとえば容器選びでは、完全オリジナルの金型を使わず、既成の汎用ボトルやチューブを活用することで、初期費用を大きく抑えられます。
デザイン面でも、華やかな箔押しや型押しといった特殊加工は魅力的ですが、コストが上がる要因にもなります。
どうしてもブランド感を出したい場合は、ラベルや外箱で工夫をするなど、加工を最小限に抑えた演出が有効です。
また、異なる商品(例:化粧水・美容液・乳液など)でも同じ容器やパッケージ資材を共通化し、ラベルだけを変更する「SKU展開」を行うことで、資材の仕入れ単価を下げることも可能です。
これは在庫管理の効率化にもつながります。
よくある失敗例とその対策
化粧品OEMでは、初めての人ほど陥りやすい落とし穴があります。
たとえば、薬機法(旧・薬事法)に違反した表記をしてしまい、販売直前で商品が差し止めになってしまうケースも少なくありません。
この対策としては、薬機法の知識を持つOEMメーカーや専門スタッフとの連携が必須です。
また、納期の遅れも頻発するトラブルのひとつ。
これは資材調達やデザイン修正に時間がかかる場合が多く、事前にスケジュール(工程表)を細かく確認し、定期的な進捗報告を受けられる体制を構築することでリスクを回避できます。
さらに、商品コンセプトと実際の中身やデザインがちぐはぐになることもあります。
たとえば「自然派」や「高級感」をうたっているのに、安っぽい見た目になってしまうと、ターゲットとのズレが発生し売れ行きに直結します。
これを防ぐためには、あらかじめブランドの世界観やペルソナを明確にした上でOEM開発に臨むことが大切です。
化粧品パッケージOEMの流れ
化粧品の中身は既製品でも、外観を変えるだけでブランド価値が大きく向上します。
パッケージデザインを差別化することで、小ロットでも世界観を演出でき、ギフト市場などで優位性を発揮します。
より詳しい内容は、下記の記事で解説しています。
→ [化粧品パッケージOEMの流れ|小ロット対応・注意点・費用相場をプロが解説]
OEMメーカーの選び方

選定時の3つのチェックポイント(対応ジャンル・実績・サポートなど)
1.希望するジャンルに強いか?
スキンケアやヘアケアなど、ジャンルによって必要な処方や原料の知識が異なるため、自社商品と同ジャンルに特化した実績があるメーカーを選ぶのが安心です。
2.過去の実績や対応ブランド例があるか?
具体的な商品名や企業名が公開されていれば信頼の証。
大手コスメブランドとの取引経験があるメーカーは、品質・対応力ともに高水準であることが多いです。
3.デザイン・薬機法・物流など、周辺領域のサポートがあるか?
単なる製造だけでなく、ラベルデザインや薬機法チェック、物流・保管の相談まで一貫して対応してくれるメーカーを選ぶと、初めてのOEMでもスムーズです。
トラブルを避けるための3つの見極め方
万が一のトラブルを避けるためにも、メーカー選びの際は以下の3点に注意しましょう。
1.連絡のレスポンスが早いかどうか
やり取りのスピード感は、プロジェクト全体の進行にも影響します。
最初の問合せや見積依頼の段階から、対応の丁寧さ・速さを確認しておくと安心です。
2.工程表や見積が明確かどうか
不明瞭な料金体系や曖昧な納期設定はトラブルの元。
納品までの工程とその中で発生する費用が明記された書類を出してくれるかをチェックしましょう。
3.契約前に秘密保持契約(NDA)を交わす体制があるかどうか
開発途中の処方やブランド情報の流出を防ぐために、秘密保持契約をきちんと交わしてくれるメーカーは信頼度が高いと言えます。
まとめ
化粧品OEMは、初心者でも比較的低コスト・低リスクでブランド立ち上げができる方法として、ますます注目を集めています。
自社の強みを活かした商品づくりを目指すなら、OEMは有力な選択肢となるでしょう。
特にパッケージデザインにこだわりたい場合は、小ロット対応かつ実績豊富なOEMパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。
ブランドや商品に合った“見た目の力”を最大限に引き出したい方は、ぜひ「I Love Paper Bag」のOEMサービスをご検討ください。







